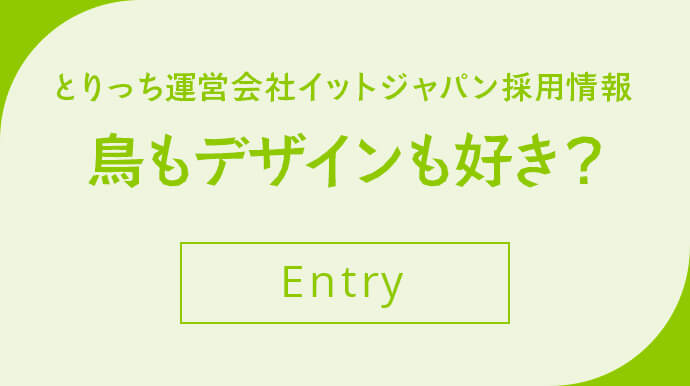【NEW】とりっち全トピックに「いいね👍」等のリアクションボタンが新登場!気持ちを気軽に伝えよう👌
鳥図鑑
コンパニオンバードが大集合。
とりっちのメンバーみんなでつくるとりっち鳥図鑑です。
オカメインコ
オカメインコ注目ランキング
-

- オカジ君
- 飼主 / ジェミー
- オレ様オカメ
- 2,716アクセス
-

- くぅちゃん
- 飼主 / ぴ-よちゃん’s
- 最初に来た子なので、少しえらそうですが皆の面倒を良く見てくれるやさしい子です。
- 2,220アクセス
-

- ぷち
- 飼主 / ぷっちぃ
- 私のことが大好き、主人と鳥は嫌い。
- 2,116アクセス
-

- パールちゃん
- 飼主 / yurichan☆
- 甘えん坊ちゃん。
- 1,812アクセス
-
- マダム(シロちゃん)
- 飼主 / 七色墨人
- マイペース、人間大好き!
- 1,645アクセス
※ランキングは直近6ヶ月のアクセスを集計
オカメインコピックアップ
オカメインコを飼っているメンバーリスト(メンバー数 1,565件)全てのメンバーを見る
-

みゆやん
オカメインコ2羽とアキクサインコ3羽...
-

中前よめ
-

purali
札幌で動物関係の仕事をしております。...
-

ひろまる
インコ好きなこどもと私。 現在セキセ...
-
けーた
うちにはコザクラインコ5羽、オカメイ...
-

海羽
オカメインコを4羽飼ってます( ´ ▽...
-
とくやん
2012年12月29日に初めてセキセ...
-

ちびちび(^−^)
コザクラインコと暮らし始めました 成...
-
Harlequin
2011.10.25 お迎えしました...
-

Atsuko
初めまして。 アニマルコミュニケータ...
-

ちいぷっぷ
-

朔ノ月
初めまして。鳥好きのお友達を増やした...
-

ありりんこ
オカメインコやマメルリハなど鳥さんを...
-

HoiHoi3
ホワイトフェイスEXヘビーパイド(♂)...
-

おキナのクッキー
鳥さん5種6羽と犬と楽しく暮らしてます。
-

メルモ
-

ピカちゃんの養母
オカメインコのヒナを飼うのは初めてな...
-

ケン
初めまして! 現在オカメインコ4羽...
-
Mrseven
イザベラの、ルーシーちゃん ルチノー...
-

とちこん
オカメインコ2羽、アオシンジュウロコ...
-

ぽんぽこぽんた
オカメとサザナミとワンコ達と、 のん...
-

ぎょく
自然に恵まれた環境で、体の療養をし...
-

ぷっちぃ
小6で初めてセキセイインコに出会い、...
-

パルちゃん
オカメインコのファンの方と色んな事話...
-

ことり
現在、4歳♂のオカメインコを飼ってます...
オカメインコについて
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 オカメインコから引用(2008.9.24 14:52)
オカメインコ(Nymphicus hollandicus)とは冠羽(かんう)[1]がある全長30cmほどのオウムである。
解説
オカメインコはオウム目オウム科に属するオウムである。和名はインコとされるがインコの仲間ではない。和名「阿亀鸚哥・片福面鸚哥」は、顔の橙色の斑点をおかめの面になぞらえたものである。
オウムの仲間では最小。尾が全長の半分を占める。精神状態によって冠羽が立ったり寝たりする。驚きや緊張を感じた時や危険を察知した状態では立ち、リラックスした状態では寝ていることが多い。
飼い鳥として日本でもポピュラーな種である。他種と一緒にいても平穏に生活し、人にもよくなつく。また容易に繁殖するが、オスメスの判断は種類によって異なる。尻尾の模様の有無や顔の模様で判断するがルチノーやアルビノなどでは外見からの識別は無理である。DNA鑑定があるが費用は高い。通常口笛を覚える方がオスである。種類によって価格に著しい差がある。品種は14種類あるが、一般的には流通しているのは10種類程度である。長年日本で簡単に巣引きされているため、中型インコと比較して最も安価で手に入る。
オーストラリアに広く分布し、群生する。オーストラリアでは最速の鳥といわれている。
成長過程
産卵
オス・メス双方(雌雄)の親鳥が巣を作り、メスが巣に産卵する。たいていは数個の卵を産む。卵の大きさはウズラの卵程度で、普通は白い卵である。雌雄共に抱卵し、日に数回餌を食べるために巣から離れる。この時期の親鳥の餌は、粟などの栄養価の高いものは控える。体力が有りすぎると、抱卵しなくなるからである。
孵化
抱卵してから3週間程度で孵化する。孵化したばかりの雛の体長は、卵の大きさから想像できるであろう。巣箱には数個の卵があることが通常であり、残りの卵も孵るまでたいてい抱卵する。
生後3週間
雛は「ジーッ、ジーッ」と鳴きながら餌をねだる。親鳥は餌を食べて巣箱に戻り雛に餌を戻して口移しで餌を与える、ということを休むことなく繰り返す。この時「キュッキュッキュッ」と音がするので、巣箱を覗かなくても餌を与えていることがわかる。オカメインコを手乗りとして育てたい場合には、生後2 週間(雛を育てるのに慣れてない人は3週間)経ってから巣箱から取り出すのが良い時期と言われている。この頃の雛は、まだ羽はない。
生後数ヶ月
ヒナを飼い始める場合、いつまでも挿し餌を続けると病気にかかる恐れがある。だがオカメインコはなかなか一人で餌を食べようとしない。周りに他の鳥がいるとそれを見て食べるようになったりする。雛の購入はなるべく自分で餌を食べられるようになった個体を選ぶのが無難である。羽はだいぶ生え揃うがまだ完全には開いておらず、一本一本がストロー状の薄い膜に包まれている。
成鳥
生後12ヶ月も経てばオスの顔の羽の色は黄色になり、雌雄の区別が容易になる。メスはお腹のあたりの羽に、波状の模様がある。もうしばらく経てば、雛を産むことができる身体に成長する。このころ、人間の年齢に換算するとおよそ18歳程度と思われる。平均寿命は15年程度で、個体によっては20年近く生きるものも珍しくない。
飼育
手乗り
オカメインコは最も人に馴れる鳥の一種である。そのため手乗りの雛を売っている。雛はひと月あまりでかなり成長し、ふた月も経つと親と同じぐらい大きくなる。ただこの段階では自分で食べる事ができない。挿し餌さをして育てるがなかなかひとりで餌を食べるのが遅い。また雛のうちは病気に対する抵抗力が弱く死にやすい。だいたい4ヶ月もすれば成長がとまり、どの個体もひとり餌になっている。人に馴れている個体の場合は雛から育てなくても手乗りのなる事も可能である。手乗りの個体の多くは飼い主にべったりし肩にいつも止まっている。ケージに入れておくと、外で遊んでほしいと鳴きさけぶ個体が多い。
オカメパニック(Night frights)
基本的に大人しく繊細な性格のオカメインコは、夜中に大きい物音がすると暴れ回る。このことを日本ではオカメパニック、英語ではNight frights(夜の恐怖)と呼んでいる。朝起きて羽が下に落ちていることがあれば、夜の間にこの現象が起きた可能性が高い。対策としては常夜灯をつけておいて部屋を真っ暗にしないこと、飼い主が起きて優しく声をかけてやること等がある。
鳴き声・声真似
* 声量は普通だが、ペット禁止のマンションなどでは特に注意が必要である。たまにオウム独特の金切り声を上げることもある。
* オスは機嫌がいいと囀る。普段おとなしくても飼い主の気を引くために大声を出す。
* 手乗りの場合飼い主に要求したり、気を引くために鳴く個体が多い。
* オスは短い単語を数語であれば覚えて喋る場合もあるが口笛の方を得意としている。
行動
* 比較的くちばしが小さいので同サイズのインコより噛む力は弱い。
* おもちゃや粟穂などを好み遊ぶ。
* 手乗りでも大人になると指より肩に乗りたがる。自分から寄ってくるが触られることを嫌う個体が多い。
* 放鳥するとたいてい飼い主の肩かお気に入りの場所にいる。
* 一日数回器用に鼻をほじる。個体によっては毛づくろいと同じ時間鼻をほじる。
餌
* ヒエ、ヒマワリ、カナリーシード、麻の実などを好んで食べる。
* ペレットを勧めるペットショップもあるが、寿命が長くなるというデータはまだ証明されていない。
飼育に関しての注意
* 呼び鳴き
手乗りの場合、飼い主を呼ぶためにひっきりなしに鳴く習性がある。また目の前に飼い主がいても注目させようと泣き叫ぶ個体が多い。
* ケージの外に出たがる
これも手乗りにしてケージの外で遊ぶのを覚えた個体の多くは、ケージから出たがるため体をじたばたしてだだっ子状態になる。
* 脂粉
羽の間から粉がたくさん出て空気中に散らばる事が多い。これは人間にはそれほど害はないと言われているが、水浴びが好きでないオカメインコはこのフケのような物を取り去ることは困難である。
* バクテリア
雛の体内にバクテリアがいて、免疫が薄れる2ヶ月ぐらいにバクテリアが体内に増えて来ると体重が減り弱って落鳥するケースが多い。特に自分で餌を食べずにいつまでも粟玉やパウダーなど流動食を与えていると、そ嚢炎や食滞を起こす。朝食べなくなったら直ぐに病院に連れて行き抗生物質とビタミンをもらう必要がある。無理矢理に粟玉やパウダーを注射器等で注入してもいつまでもそ嚢の中に餌が残り、逆にそこにばい菌が繁殖して命を落とす。元気なうちならヨーグルトなど乳酸菌を与える事で予防できる。
品種
品種は主に体の羽色と模様、顔部分の色で区別される。ルチノー系は色素が薄いため、黄色をしている。さらに目が赤くて、本来のオカメインコより目が悪いと言われている。ルチノー系の他にグレーの原種のものをノーマル、うす茶色のものをシナモン(イザベラ)、色素がなく真っ白なものをアルビノ(WF・ルチーノ)、部分的に色抜けがあるものをパイド、羽にうろこ模様が入っているものをパール、ほっぺの日の丸が淡い黄色のものをイエローフェイス、オレンジのものをパステルフェイス、日の丸がないものをホワイトフェイスと呼ぶ。下記のGalleryにある画像も参照。
ペットとしての歴史
* オカメインコはオーストラリアの内陸部に群れをつくって生息しているが、イギリス人が本国に持ち帰りペットとして広まったのが200年ぐらい前である。
* 学名の「Nymphcus hollandicus」はオーストラリアを初めて本格的に調査したオランダ人がオーストラリアを「ニュー・オランダ」と名付けたことから、「Psittacus novae-hollandiae(ニュー・オランダのオウム)」と呼んでいたものを1832年にドイツのヨハン・ワーグラーにより「ニュー・オランダの妖精」という意味で付けられた[2] 。
* 英名の「Cockatiel」(コッカティル)は1845年にヨーロッパでペット目的の繁殖が行われた時に、ペット業者がポルトガル語の「Cacatilho」(小さなオウム)を元に名付けたとされる[2] 。
* 品種改良は50年ほど前から始まり、10年ごとにパイド、ルチノー、パール、WFと誕生し現在ではその組み合わせで何種類もできたのである。
* 日本には明治末期の1910年代に輸入され、ペットとしての歴史は意外と長いが原種の色合いが地味なことから同じオーストラリア産のセキセイインコなどと比べると全く普及せず、1960年代頃までセキセイインコの10倍以上の価格が付けられていた。しかし、ルチノーなどの品種が開発されると徐々に人気が上がり、現在ではペットショップで普通に見かけるほどになった。
ここまで